性愛に踏み出せない女の子のために 第8回第二部 後編 宮台真司
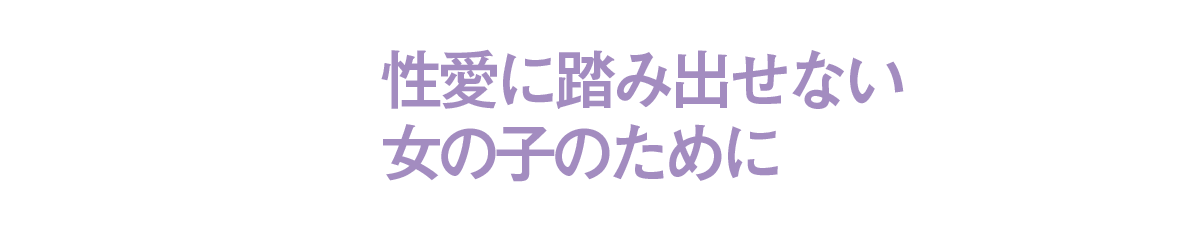
性愛に踏み出せない女の子のために
第8回第二部 後編 宮台真司
雑誌「季刊エス」に掲載中の宮台真司による連載記事「性愛に踏み出せない女の子のために」。今回で第8回をむかえますが、二部に分けて、WEBで発表いたします。社会が良くなっても、性的に幸せになれるわけではない。「性愛の享楽は社会の正義と両立しない」。これはどういうことだろうか? セックスによって、人は自分をコントロールできない「ゆだね」の状態に入っていく。二人でそれを体験すれば、繭に包まれたような変性意識状態になる。そのときに性愛がもたらす、めまいのような体験。日常が私たちの「仮の姿」に過ぎないことを教え、私たちを社会の外に連れ出す。恋愛の不全が語られる現代において、決して逃してはならない性愛の幸せとは?
第8回第二部は、後編として、「自我の働き」「精神の生態学」といった理論的なテーマも含んだ話題です。
過去の記事掲載号の紹介
第1回は「季刊エス73号」https://amzn.to/3t7XsVj (新刊は売切済)
第2回は「季刊エス74号」https://amzn.to/3u4UEb0
第3回は「季刊エス75号」https://amzn.to/3KNye4r
第4回は「季刊エス76号」https://amzn.to/3I6oa57
第5回は「季刊エス77号」https://amzn.to/3NRfjYD
第6回は「季刊エス78号」https://amzn.to/3xqkU0V
第7回は「季刊エス79号」https://amzn.to/3QiyWuP
宮台真司(みやだい・しんじ)
社会学者、映画批評家。東京都立大学教授。90年代には女子高生の援助交際の実態を取り上げてメディアでも話題となった。政治からサブカルチャーまで幅広く論じて多数の著作を刊行。性愛についての指摘も鋭く、その著作には『中学生からの愛の授業』『「絶望の時代」の希望の恋愛学』『どうすれば愛しあえるの―幸せな性愛のヒント』(二村ヒトシとの共著)などがある。近著に、『崩壊を加速させよ 「社会」が沈んで「世界」が浮上する』。
聞き手
イラストを描く20代半ばの女性。二次元は好きだが、現実の人間は汚いと感じており、性愛に積極的に踏み出せずにいる。前向きに変われるようにその道筋を模索中。
後編
自我の働き 自己防衛を軽くする
──「こども性教育」のワークショップを記録した『こども性教育』は、子供たちから「恋愛がしたい」「本当にしたい恋愛はこういうもの」という願望が引き出されていて、素敵でした。でも、フェミニストを語る一部の方たちが、援助交際を肯定する者にワークショップをさせるのか、変性意識状態につけこむ非合意性交を広めるのかと、場を提供した和光大学や、お勤めの都立大学に抗議する動きもあったそうですね。
宮台 援助交際について90年代に書いた主要な論点は3つです。第1は、ヨーロッパの過半の国が売買春を合法化する理由。具体的には、売る売らないは自分が決めるという「自己決定権の尊重」、非合法化してもなくならない売買春の「合法化による管理可能化」、近代社会の原則である「法と道徳の分離(特定者だけが合意する道徳を法化するな)」です。
第2は、合法化国が性交合意年齢より売春合意年齢を3〜5歳高く設定する理由。高校生になれば性交はOKでも成人するまで売春はNGとかです。具体的には、附従契約(地位の優劣に影響された非対称な合意)の阻止。買春する成人の3万円より売春する高校生の3万円の方が遙かに貴重なので不利な契約に合意して尊厳を毀損されがちなのを、防ぎます。
第3は、これらの情報がネットで入手できる時代に「所詮はあんたの道徳」に過ぎない道徳的説教は無効で、「社会学的啓蒙」だけが有効なこと。中編で話した通り、学問的成果を元に当事者に見えにくいリスクを伝え(情報非対称性の克服)、当初思い込んだ合理性を考え直してもらう。抽象的には「選択肢を評価する能力を上げて選択肢を増やす」戦略です。
以上は、94年の『制服少女たちの選択』や97年の『まぼろしの郊外』『性の自己決定原論』に書きました。そこには援助交際の単純な否定も肯定もありません。「宮台=援助交際肯定」と思い込む言葉の自動機械=クソフェミは、僕の本を読んでいないか、読解力が小学生以下であるかです。自分の頭の悪さを棚に上げて、イメージだけで語っているのですね。
変性意識状態については、2010年代以降の『愛のキャラバン』『希望の恋愛学』『どうしたら愛し合えるの?』で書きました。主要な反論は二つ。第1は、この概念を言外・法外・損得外での身体的・感情的な研ぎ澄ましに限定して用いていること。催眠や薬物の肯定どころか、むしろ完全に否定している。この連載を読んで来られた方にはあまりにも自明ですね。
第2は、言葉での合意が要らないのではなく、言葉での合意では足りないと語って来たこと。例えば、劣等感を抱く部分を言葉巧みに褒めれば人は容易く変性意識状態に陥って(=言葉に飲まれて)性交に合意します。それを避ける唯一の方法は、「言外・法外・損得外の時空での豊かさ」を「相手の言葉の外側で」触知する能力を上げること。連載で語ってきました。
これらの反論を各所で示しましたが、クソフェミからの再反論はなく、反論済みの論点をボット(言葉の自動機械)的に反復するだけ。また、クソフェミ論客にウリセン(男娼)にハマっていた者やステレオタイプの権化であるホスト好きがいる事実が拡散されて「価値や倫理より、ポジション取りに熱心な醜悪さ」を知る者が増え、既に影響力が激減しました。
なお「クソフェミ」とはフェミニズムへの蔑称ではなく、フェミニストを自称しつつフェミニズムの思考伝統を毀損する者を言います。安藤優子氏との動画「フェミニズムとは何か?」で話した通り、第3期までの(正確には第4期の一角をなすLGBTQをも含む)フェミニズムの一貫した思考伝統は、カテゴリーに結合したステレオタイプへの批判です。
第1期は、女の政治参加を阻むステレオタイプへの批判(普選運動ほか)。第2期は、政治参加しても政治的主張にバイアスをかける私領域でのステレオタイプへの批判(性別役割批判ほか)。第3期は、「女らしさは私が決める」とステレオタイプから自由な営みの具体的実践(ギャル文化の発信など)。ここまでは「ステレオタイプから、より自由になる動き」です。
第4期はLGBTQとネットフェミニズムを含みますが、後者の一部に「男は敵!」「『男の性欲』は女の支配!」「『女の魅力』は男への媚び!」とする、カテゴリーにステレオタイプを結合して女の自由を奪う、希望ベースより呪いベースの差別主義者=言葉の自動機械が、湧きます。フェミニズムの思考伝統より「中国人は敵だ!」的ウヨブタに酷似します。
社会学者としては、ネット2.0化(ブログからSNSへ)に伴い、「中国人は敵だ!」的ウヨブタと「男の性欲は敵だ!」的なクソフェミが並行して増殖したのが興味深いです。「言葉の自動機械」は、トラウマに由来する不安の埋め合わせという神経症の典型症状です。多くの人は「自己像の悪さ」に由来するダサさを直観。神経症的な批判にエゴイズムを感じます。
必修授業では、「フェミニズムに興味があるか?」との問いには男女を問わず大半が手を挙げますが、「フェミニストになりたいか?」との問いに手を挙げる人はほぼいません。学生たちは、前者を長い思考伝統への興味についての質問だと受け取り、後者を今のネットフェミニズムに連なりたいかという質問だと受け取るからだと言います。理解できる感覚です。
そこに、今時のフェミニスト((ソフェミ)になれば性愛の豊かな経験から疎外されるという正しい直観と、「自己像の悪さ」を離脱する努力をする代わりに他責化と攻撃に勤しむインセルに酷似した人とは友達になりたくない・自分がそれをすれば友達を失うからイヤだという健康な感情(後者は柴田英里氏の私信に於ける分析)を、看て取れるからです。
クソフェミによる様々な批判は、ウヨブタと同じで、批判される側の「社会」の問題より、所詮は批判する側の「実存」の問題だろうという話です。でも、そうした「実存」──トラウマに由来する不安の埋め合せとしての各種の「言葉の自動機械」──が、或る時期から蔓延してきた事実は、それ自体、明白に「社会」の問題を指し示していると言えます。
どんな問題か。中編では、性愛の「退却系・テンプレ系・肉食系への3類型化=広義のテンプレ化」の背景を縷々語りました。一口で言えば、80年代からの新住民化・に由来する親子関係への閉ざされ・に由来する「自己像の悪さ」・に由来する関係性(踏み込み・踏み込まれ)の忌避・に由来するキャラ&テンプレ化・の世代的昂進、という生態学的展開でした。
既に御明察の通り、SNS化に伴って湧いて来たウヨブタとクソフェミは、この生態学的展開の一角をなします。それで終了しても良いですが、こうした生態学的展開の中で、「自己像の悪さ」を離脱する努力をする代わりに他責化と攻撃に勤しむ人達が、なぜ増殖したのかを、連載で触れてきた前期後期のフロイト図式の復習も兼ねて、一瞥しておきます。
──以前、お聞きしたところでは、前期フロイトは、前意識・意識・無意識の3項目を使い、後期フロイトは、エス・自我・超自我の3項目を使う、ということでした。でも、あんまり中身を覚えていないので、ありがたいです。
無意識・前意識・意識の 量子脳論的な再解釈へ
宮台 まず、論理的な推定から始めます。男との性愛的な関係性から享楽を得て来た女が、「男の欲望は敵!」「萌え絵は敵!」「アダルト映像は敵!」の類の、カテゴリーにステレオタイプを脊髄反射的に結合する「恨みベースの差別主義者」になることはあり得ません。また広義のテンプレ系(退却系・テンプレ系・肉食系)ですら、そうなることはあり得ません。
次に、僕の周囲でクソフェミ化した女を観察したり、周囲にクソフェミ化した女がいる人達から聴き取ると、DV被害を含めて例外なく男関係で失敗を重ねています。願望を前提とした期待外れがあるのです。でも、それだけでは過剰な攻撃には繫がりません。過剰な攻撃には必ず前提となる依存があります。とすると、その願望は「依存を含む願望」です。
『まぼろしの郊外』に複数の事件に即して述べました。70年代後半に噴出した(子供から親への)家庭内暴力も、80年代前半に噴出した校内暴力も、家族や学校への願望と結びついた期待外れによる「依存的暴力」でした。共に「自分がこうなったのはお前たちのせい!」という、「自己像の悪さ」による不安を「他責化(での恨み)」で補償するメカニズムがあります。
クソフェミへの道程も、依存→裏切られ→依存→裏切られ→…の繰り返しで「自己像の悪さ」を抱えたのが出発点だと推定できます。そこには「依存→裏切られ→自己像悪化→更なるの依存→裏切られ→更なる自己像悪化→…」の自己強化的循環があります。そこに救世主として「あなたは悪くない、そもそも男が敵なのだ」というクソフェミ言説が登場します。
何かに似てますね? 中編で話題になった、「喋れなかった男が、セクトに『君は悪くない、悪いのは社会だ』」と、「自己像の悪さ」による不安を「他責化」で補償され、前に踏み出せるようになった逸話です。ただしこの話には、自分の口から溢れ出るセクト言説を自己観察し、自分は入替可能な自動機械じゃないかと気付く話が続きました。それが希望を与えます。
どんな希望かは後で話します。話を戻すと、セクトに救われた男には「人前で自由に喋りたい」という願望があり、クソフェミ言説に救われた女には「男と素敵な関係になりたい」という願望があるのも共通します。また、願望の達成で「自己像の悪さ」から離脱できるのに、達成できずに「自己像の悪さ」が続いたり昂進したりしているのも、共通します。
そこから浮上するのは、本当に救われているのか、無意識を抑圧しているだけでは、という共通の問題です。「資本主義は敵だ!」とするセクト言説への依存が「資本主義は結構いい」という無意識を抑圧し、「男は敵だ!」とするクソフェミ言説への依存が「男は結構いい」という無意識を抑圧するので、人々はそこに強迫神経症的な「不自然な依存」を感じます。
クソフェミに絞ります。「男は敵だ!」的言説への依存は、「自己像の悪さ」の昂進による不安に耐えられないからです。でも無意識には「男と素敵な関係が欲しい」という願望を蓄蔵しているので、昂進停止で前に進めるようになっても(=「自己像の悪さ」に耐えられるようになっても)「自己像の悪さ」自体は解決しません。精神分析は次のように記述します。
素敵な関係を願望するのに挫かれ続けて来たという時間軸・が与える「自己物語(自己像)の悪さ」の昂進による不安・の埋め合せとしての「男は悪いもの」という他責化は、元の願望に含まれる「男は善い」のイメージを抑圧します。だから、「男が悪い/自分は善い」の意識が、逆転図式である「男は善い/自分が悪い」という無意識の内圧を高めざるを得ません。
そんな人々が男と良好な関係にある女を見ると、抑圧された無意識が刺激されて不安を覚えます。不安の埋め合せで、「男が悪い/自分(女)は善い」の意識にしがみついた攻撃が強迫的に先鋭化します。ここで「前意識」概念を持ち込み、更に詳しく記述します。ここから先、ペンローズの量子脳仮説を参照して、「前意識」概念を規定し直すことから始めます。
前意識とは、「無意識=隠喩的二項図式群」によって前提付けられた(=場を与えられた)意識=散文」となりうる散文群・から成る確率雲です。電子雲同様、存在確率ではなく並行存在の重み付けです。謂わばぼんやりとした思考の連続体。それが発話や書記の度に──喋ったり書いたりするごとに──シュレディンガー方程式的に収縮し、その都度の意識を与えます。
確率雲的な前意識が意識に収縮すると、それに基づく行動と体験で、確率雲的な前意識自体が変化します。それが、「前意識(確率雲としての散文群)→意識(収縮が与えた散文)→変化した前意識(新たな確率雲としての散文群)→変化した意識(新たな収縮が与えた散文)…」という経路依存的な水平的=物語論的拘束を、その都度の意識(散文)に対して与えます。
他方、相対的に変わり難い無意識=隠喩的二項図式群は、前意識(確率雲としての散文群)に影響する磁場を構成することで、経路に依存しない垂直的=神話論的拘束を、その都度の意識(散文)に対して与えます。つまり、無意識の磁場が、前意識の確率雲と意識の収縮位置の、経路依存的な展開を介し、その都度の意識(収縮位置)を、間接的に方向付けます。
つまり、同一の無意識(隠喩的二項図式群)が、前意識の確率雲と意識の収縮位置の経路依存的展開次第で、散文的意味が互いに対立する別の意識をもたらし得るのです。無意識から見ると、意識は偶発的、つまり他であり得るのです。だから、前意識と意識の経路依存的展開に介入すれば、無意識の隠喩的二項図式が不変でも、違うイデオロギーに導けます。
例えば、同じ無意識を抱えたまま、経路次第ではウヨブタ的意識もクソリベ的意識も持ち得ます。実際ウヨブタとクソリベの間を振動する人がよくいるでしょう。クソフェミについて言うと、たとえ挫折を繰り返したにせよ、初発の願望に関わる「男は善い/自分が悪い」の無意識の上で、経路次第で全く別の意識に導かれる可能性があったということです。
パラメータ次第で同じ遺伝子型が対照的な表現型を導く、とする遺伝学の知見に似ます。かくして前期フロイトの「無意識・前意識・意識」を理解した上での自己省察で、イデオロギー(言葉の自動機械的な枠組)への固執を離脱する可能性が見えて来ます。それが先の希望です。だから、ウヨブタ・クソリベ・クソフェミの言説(意識)を真に受けるのは得策ではない。
僕が長らく「これらの言説は症状に過ぎない」と繰り返して来たのは、こうした「表現型の偶発性」に止目するためです。ちなみに様相論理学では、「偶発的」とは「可能だが必然ではないこと」=「他であり得ること」を指します。それを踏まえて言えば、無意識を変えられなくても、その表現型としての意識は、偶発的=他でもあり得るということなのです。
フロイトによれば、「死の不安」など<対処不可能な不安>を、「元栓を閉め忘れたかも」の類の<対処可能な不安>に置き換え、「死の不安」から見れば無意味な対処を反復するのが、強迫神経症(今日の強迫性障害)です。無意識に於ける「死の不安」に対し、「元栓を閉め忘れたかも」の意識は、「鍵を閉め忘れたかも」などに置き換え可能な、偶発的な症状です。
──自分の言葉や他人の言葉に、文字通りに反応するんじゃなくて、それぞれどんな無意識の表現型なのかに注意した方が良いということですね? また、同じ無意識がどんな表現型として表れるかは、一つに決まっているわけじゃなく、同じ無意識が、偶然のいきさつ次第で、一見すると対立し合う言葉の、どちらも導くことがあるということでしょうか。
宮台 はい。その「偶然のいきさつ」を記述するべく持ち込まれたのが前意識の概念です。無意識の磁場に支えられるのが前意識のクラウドで、そこから様々な偶発的体験を引き金として降りてくるのがその都度の意識です。何を意識したかで行動と体験が変わるので、前意識のクラウドが少しずつ変わり、そうした偶然の累積次第で異なる「思想」に到ります。
これは精緻な「精神の生態学」ですが、すぐ分かるように「社会の生態学」との関わりが不明確です。ちなみに生態学とは生態系を記述する学問で、生態系とは「前提づけるもの」と「前提づけられるもの」の線形・非線形的ネットワークの総体です。線形とは比例的・階層的な関係を言い、非線形とは階層内のループや階層間の飛び越しを含む関係を言います。
「精神の生態学」と 「社会の生態学」の結合
宮台 そこに登場するのが後期フロイトのエス・自我・超自我の3元図式。ざっくりエスとは、「無定型なエネルギーの発信源」。超自我とは、それを成形しようとする社会の働き・を内面化した「社会の代理人」。自我egoとは、この二つを要件として働く、「直接すぎる反応(反射)」や「極端すぎる反応(過剰反応)」から自己selfを防衛する「適切化メカニズム」です。
エスは自我に無定型なエネルギーを供給します。他の動物ではエネルギーと発露形式が一体で「本能」と呼びます。ヒトはエネルギーの発露形式が未然なので「欲動(古くは衝動)」と呼びます。でも、ヒトは発露形式を後天的に学び、それを自我に内蔵します。超自我は、かかる自我の適切化メカニズムを、社会と両立可能なものに方向付ける機能を果たします。
超自我は、代理人(父の名)を通じた「社会(大文字の他者)からの抑圧」が作り出す心の中の「社会の代理人」です。中編で触れたミードは、同時代人フロイトの超自我概念の影響で「一般的他者の役割取得」の概念を立てます。そこに含意されますが、「社会からの抑圧」は圧縮表現で、実際には、父相手に限定されない複雑な関係性の履歴による効果です。
ミードは重要な社会学者として知られますが、彼の理論を熟読すると、後期フロイトの「精神の生態学」を「社会の生態学」に繋げる試みだと判ります。後期フロイトの3元図式(エス・自我・超自我)自体が「社会の生態学」を意識したものだからだというのが僕の見立て。ちなみに1950年代にはパーソンズが自らの社会システム理論にフロイトを組込んでいます。
超自我は、規範受容と同時に、規範破壊を享楽する、元はエス由来のカオス的エネルギーを蓄積します。これは、エスの無定型なエネルギーを規範受容で抑圧することによる内圧上昇のせいです。意識が規範に従う際に無意識が自動的に蓄積する逆転図式として前期フロイトが記述したもので、これを無意識から見ると、意識が無意識の反動形成となります。
反動形成は、性欲を良からぬものとする社会規範の想定可能性を当てにして、強い性欲(無意識)を覆い隠すべく過剰な性欲攻撃に乗り出す営み(意識)が典型で、強迫神経症に含まれます。規範受容と規範破壊を同時に志向する超自我の二重性は、カテゴリーに結合したステレオタイプ・を強迫的に反復するクソフェミ・に潜在する願望(欲望)の理解に役立ちます。
──同時に反対のものが刷りこまれるというのは興味深いですね。
宮台 フロイトの反動形成の理論は、フーコー『性の歴史』第1巻『知への意思』でのビクトリア朝分析で再演されます。英国ビクトリア朝と言えば性的禁圧の厳格さで知られますが、これは性的禁圧の狂熱というべきもので、そこに見出されるべきなのはむしろ強い性的欲望だとして、社会的に大規模な反動形成を見出したのが、1976年のフーコーでした。
「クソフェミって嫉妬ですか」と幾度も質問されてきた経験から推察して、フロイトやフーコーを知らずとも、性欲を男根的なもの=男による女支配(への女の服従)として攻撃するクソフェミの超自我的二重性を、多くの人が直観しています。この嫉妬を、「性愛の不自由による劣等感で、性愛が自由な人に嫉妬してるのですか」と丁寧に表現する人もいます。
重要なのは「(社会が刻む)否定的自己像ゆえの不安→他責化で不安を埋める(社会からの)規範の受容→それによる欲動の抑圧→超自我的二重性による(社会的言説の)過激化」という「精神の生態学」です。ちなみに「(社会的言説の)過激化」を他の人たちが「他責化で不安を埋める(社会からの)規範受容」に使うので、そこに複数主体間のマッチポンプを見出せます。
丸括弧内に注目。後期フロイトは超自我論(に流れ込む前期の反動形成論)が「精神の生態学」と「社会の生態学」のインタフェースを与えているのが判ります。これらのインタフェースが社会的介入の可能性(という希望)を示唆します。具体的には、①自己像悪化を招く社会関係への介入。②社会的規範の布置への介入。③社会的言説の妥当性への介入です。
「風の谷」旅芸人プロジェクトは 精神と社会のインタフェースに介入
宮台 種明かしすると、この連載は、準備中のワークショップ結合組織「『風の谷』旅芸人プロジェクト」との合体で、①自己像悪化を招く社会関係への介入、②社会的規範の布置への介入、③社会的言説の妥当性への介入を、達成する実践の一部です。実際、①自己像悪化を招く社会関係、②社会的規範の布置、③社会的言説の妥当性について「目から鱗」だったはず。
このワークショップ結合は、幼保の「森のようちえん」実践、小中学生の「森のキャンプ」実践、小中高大生の「恋愛ワークショップ」実践(『こども性教育』)、中高大生と大人の「宗教ワークショップ」実践、大人の「親業ワークショップ」実践(『ウンコのおじさん』)から成り、『こども性教育』『ウンコのおじさん』はその試行的実践の記録です。
再び性愛に焦点を絞ると、クソフェミの出発点にある「依存→裏切られ→自己像悪化→依存→裏切られ→自己像悪化…」の<自己強化的循環>と、それを含む「親への依存(裏切られ)→男への依存(裏切られ)→クソフェミ・ウヨブタ・カルト言説への依存(裏切られ)」の<依存先渡り鳥>は、人を依存の道具として使う醜悪な「他者の物格化」を共通項とします。
「物格化」は「人格化」の対立概念で、他者を物格化する自分に気付けるか否かは、人格化し合う関係(=なりきり合う関係)が与える享楽を想像できるか否かで決まります。人格化し合う関係が与える享楽を想像できるか否かは、人格化し合う関係が与える享楽をどれだけ(現実に・想像的に)体験してきたかで決まります。僕らはこの体験に照準するわけです。
物格化し合う関係は、双方に自分の入替可能性を意識させて不安が生じます。これがテンプレ系の不安。不安は埋め合せ(補償)を要求します。要求に応えるのがインスタでのいいね掻き集め。だからテンプレ系にはインスタがつきものです。補償は元の不安を放置します。神経症図式です。異常なので一部は退却化し、ツマラナイので一部は肉食化します。
でも退却系もテンプレ系も肉食系も人格化(なりきり合い)の回避(関係性よりキャラ)という点で全て広義のテンプレ系で、人格化が与える享楽を知らないままです。比較可能な快楽の多寡に過ぎないので、肉食系はやがて飽きて「別のことをしてる方が楽しい」となり、テンプレ系も退却系から移行してしばらく経つと「別のことをしてる方が楽しい」となります。
人格化の回避としての広義のテンプレ系は定義的に「言葉の自動機械=クズ」です。クズという物言いは、「これでいい」と自明性に閉ざされた者に衝撃を与えるための選択です。あなた方が「自分はクソフェミじゃない」と思っても、「関係性よりキャラ」である限りはクソフェミと同じ平面にいます。実際このクズ平面がクソフェミを生み出す母体なのです。
理論社会学者としては「クズが悪い」と言って済ませるわけには参りません。「精神の生態学的展開」の背景に必ず「社会の生態学的展開」があります。具体的には、80年代からの新住民化・に由来する親子関係への閉ざされ・に由来する「自己像の悪さ」・に由来する関係性(踏み込み・踏み込まれ)の忌避・に由来するキャラ&テンプレ化・の世代的昂進です。
一口で「クズになったのは育ちが悪かったから」です。つまり社会化という自然過程の帰結です。ただし注意点が二つ。第1に、ここでの「育ち」とは体験できた関係性の謂いです。第2に、先の図式通り「精神の生態学的展開」と「社会の生態学的展開」は交互に条件付け合うので、関係性から見た社会化の環境が加速的に悪化し、世代的に昂進しています。
でも、社会化の環境改善は、立法の如きマクロな制度変更では論理的に不可能です。第1に、法(制度)は言葉・法・損得の界隈での適応圧力の向きを変えるだけ。言葉・法・損得を越えた関係性を促すのは不可能でなくても難しい。不可能ではないのは、新住民化(安全・便利・快適化)以前の法に戻せば、言外・法外・損得外で同期する営みが一部回復し得るからです。
そこに第2の問題が立ちはだかる。法変更の手綱を握る人々が既に「育ちが悪い」。『まちづくりの哲学〜都市計画が語らなかった「場所」と「世界」』『神なき時代の日本蘇生プラン』で実例を挙げた通り、言外・法外・損得外で同期する営みを力づけるには、育ちが悪いクズによる住民民主主義を排除した、①知識社会化を促す②有力者の権力行使が必須です。
これはアーキテクチュラルな権力の形をとります。代官山では賢明な大地主と彼が組織した知識人集団が商業地域を阻止して第二種低層住宅専用地域のゾーニングを貫徹しました。ざっくり店舗にオーナー家族が住む形しか認めず、そこから先に初めて人々の自由と民主主義を認める。すると「資本主義的営みで人間関係が失われる弊」を阻止できるのです。
『神なき時代〜』に詳述した通り、「資本主義(経済)×民主主義(政治)」より「資本主義(経済)×権威主義(政治)」の方が、「資本主義が社会を(システムが生活世界を)台なしにする弊」を阻止するには合理的とする発想(新反動主義)が拡がった理由が、クズによる民主主義です。僕はそれに与せず、「社会という荒野を仲間と生きる」共同体自治を推奨しています。
「社会という荒野を仲間と生きる」共同体自治に必要な「同じ世界で一つになる」感情と身体の能力を涵養する実践が『風の谷』旅芸人プロジェクト。その一部に「恋愛ワークショップ」(と機能的に等価なこの連載)を含むという建て付けです。「精神の生態学」と「社会の生態学」の相互嵌入に鑑みれば、恋愛の不全を、恋愛にだけ注目して解決するのは無理です。
超自我と無意識の関係 「人が変わった」が起こるわけ
宮台 「精神の生態学」に戻ります。超自我は規範図式と逆転図式の二重性です。規範図式(例えば「大人は快/子供は不快」)と逆転図式(「子供は快/大人は不快」)は共に隠喩的二項図式から成り、共に前意識クラウドに磁場を張ることで、クラウドから降りてくる意識に影響します。フロイトは無意識(前期)と超自我(後期)の関連を明示しませんが、そう考えられます。
数多の主題について規範図式と反転図式の二重性が誰にでも存在しますが、どちらが前意識クラウドへの磁場を介してクラウドから降臨する意識として顕在化しやすいかは人によって違います。僕の考えだと、前意識クラウドには、規範図式に基づく確率雲と、逆転図式に基づく確率雲が、謂わば「色が違う雲(青い雲・赤い雲)」として重なり合っています。
偶発的な引き金(いつどんな環境で何を喋る・書くか)次第で、意識は青い雲からも赤い雲からも降臨し得ますが、ランダムな引き金に対する降臨確率のスペクトラム(確率雲的な連続体)が人によって違います。意識が青い雲から降臨しやすかった人が赤い雲から降臨しやすくなると、「人が変わった」と周囲が感じます。こうした変化はなぜ生じるのでしょうか。
先に「精神の生態学」を話した際でも良かったのですが、読者のキャパをオーバーフローする可能性があったので、改めて話します。無意識での規範図式(A=快/B=不快)と逆転図式(B=快/A=不快)の重ね合せに於ける重み付けの変化で、シュレディンガー方程式的収縮で意識を降臨させるクラウド分布に変化が起こり得ます。垂直的ロジックの変化です。
他方「前意識クラウド→降臨した意識→意識による行動と体験→前意識クラウドの変容→降臨する意識の変化…」でもクラウド分布の変化が生じます。水平的ロジックの変化です。無意識は変わり難いとされます。規範図式と逆転図式の重ね合せは変わり難い。でも重み付けがどれだけ変わり難いのかは事前に判らないので、働きかけ実践の指針になりません。
他方、行動と体験によって変わる「前意識クラウド→降臨した意識→意識による行動と体験→前意識クラウドの変容」は通常「経験で構えが変わる」と呼ばれる事態なので、働きかけ実践を計画しやすい。与えられた主題について前意識の青い雲・赤い雲のいずれから意識が降臨しやすいかの確率を、特定の行動と体験を促して変容させる戦略が現実的なのです。
かくて変容する前意識クラウドの長い時系列が、無意識での規範的二項図式と逆転的二項図式の重ね合せに於ける重み付け=磁場の発現しやすさを変えることはあり得ます。でもハナからそれを目指すのは悪手。親が貼ったラベルを剥がす実践も、本当は望んでいなかったと「思い出す=意識する」ことで、どの雲から意識が降臨しやすいかを変える営みです。
ただし幼少期は無意識に於ける超自我的二重性機能の形成途上なので、幼いほど無意識が変容しやすいでしょう。だから、子供達への処方箋としては言葉の効力を奪う=言葉の外に開く働きかけが合理的で、大人達への処方箋としては言葉のラベルを引き剥がす=既存の自己像(自己物語)から自由になる働きかけが合理的です。合理性の分布は個人ごとに違います。
「森のようちえん」実践や「森のキャンプ」実践が思春期前の子供を対象とするのに対し、「恋愛ワークショップ」実践が思春期以降の青少年を対象とするのはそれが理由です。80年代初頭に体験したアウェアネストレーニングでは自己物語からの解放で性愛の構えと行動が激変するのを幾度も目撃しました。無意識の書き換えではないので性格は変わりません。
科学と接合した実践の指針には 後期フロイトより前期フロイト
──心の働きをここまで分解して考えられるというのも、それを踏まえてワークショップをデザインできるというのも、ちょっとした驚きです。
宮台 フロイトの一貫した思考は「心は機械だ」というもの。機械だから設定があります。変えやすい設定と変えにくい設定があります。機械だから作動目的(果たすべき機能)があります。こうした機械としての心の側面が自我です。後期フロイト3元図式(エス・自我・超自我)では、自我に必須の、特定機能を果たす補助装置として、エスと超自我を想定します。
エスは、無定型なエネルギーの発信装置です。超自我は、無定型なエネルギーの発露に社会に適合した型を与える装置です。自我egoは、エスと超自我をサブ装置として伴いながら「直接すぎる反応(反射)」や「極端すぎる反応(過剰反応)」から自己self(生体)を防衛する装置です。ざっくり自我とは、自己防衛の機能を果たす脳神経学的機能連関の総体です。
この自我には意識が含まれます。意識の特徴は意識を意識する再帰性です。意識を意識する意識を意識する意識…と累加します。その営みをリフレクション(反省)と言います。リフレクションは脊髄反射や過剰反応などのリフレックス(反射)を反応のラグ(遅延)を伴いつつ抑止する適切化メカニズムとして機能し得ます。でもそう機能しないこともあります。
なぜなら脳神経学的機能連関の中に意識できない領域があるからです。こうして前期フロイトは、意識が意識できる度合によって、脳神経学的機能連関を3領域「意識・前意識・無意識」に分けました。後期フロイト3機能「エス・自我・超自我」論から見ると、3機能が意識から見てどこにあるかを記述するのが、前期フロイト3領域「意識・前意識・無意識」論です。
後期フロイト3機能「エス・自我・超自我」論と前期フロイト3領域「意識・前意識・無意識」論がどんな関係にあるかは、フロイトが明示しないので諸説ありますが、どうでもいい。3機能論が「機能の視座」から、3領域論が「過程の視座」から、脳神経学的機能連関を記述するだけです。量子脳仮説のような科学と接合するには「過程の視座」の方が扱いやすい。
なので、僕自身は、「隠喩的磁場(無意識)→散文的確率雲(前意識)→散文的収縮(意識)」という「過程の視座」を軸に、そこでの過程的処理(プロセシング)が3機能「無定型な力(エス)→社会適合的な成形(超自我)→直接反応・過剰反応の抑止(自我)」をどう現実化するか・しないかという「機能の視座」を時折加えつつ、過程的処理を記述する方法を選択します。
ただし科学哲学から見て、フロイトの精神分析学(やラカンの改訂版)は特殊な学問です。脳神経学的機能連関を記述するとはいえ、解剖学的実証とは無関連で、妥当性が「理論的仮説に基づく実践が現実に有効か」という臨床的評価に依存するからです。この正当性調達の形式は、気功や整体に似ます。実践の有効性が、実践を導く枠組を正当化するのです。
妻の逆子を10分の手かざしで治し、妻の歩行不能なほど重度な椎間板ヘルニアを週1度頭部を触って1か月で完治させ、僕の脳ドックで見つかった脳梁の小豆大の腫瘍を月1度頭部を触って半年で完治させた、超一流の整体施術師に、どんな理論枠組に基づく実践なのかを尋ねたら、詳細に説明して貰えましたが、こう付け加えるのを忘れませんでした。
でもね、宮台さん。気功にもほとんど同じ有効な実践があるんだよ。でも、それを導く理論枠組が違うんだ。気功は、共時的な気(エネルギー)の循環過程に注目した理論枠組で、整体は、歴史的な二足歩行動物の進化過程に注目した理論枠組だ。ところが実践を観察するとほとんど同じ施術をする。異なる理論枠組が、有効な同じ施術を導くんだ。どういうことかね。
同じことがフロイトの前期後期にも言えます。前期フロイト3領域「意識・前意識・無意識」論(局在論)に基づく施療と、後期フロイト3機能「エス・自我・超自我」論(構造論)に基づく施療が、一部の精神症状に対してはほとんど同じものとなり、それが有効な臨床的帰結をもたらすので、当該の精神症状に限れば、3領域論も3機能論も同様に妥当ということになります。
理論の妥当性を評価する外部基準が「観測との合致」か「実践の有効性」かの違いはあれ、ニュートン力学と特殊・一般相対性理論との間にも、対象の相対速度が光速より大幅に小さい・重力が小さいなどの条件次第で、全く異なる理論枠組が同じ記述性能を持つ関係があります。ただし記述性能は限界事例に於いて差を示します。これはフロイト前期後期も同じです。
精神分析学の特殊性は、理論の外部基準が、実践の有効性にあることです。実践の有効性は実践目標に依存します。実践目標(の社会的意義)を共有しないと理論の評価に合意できません。観測との合致ほど判定が単純ではないのです。ちなみに通常の自然科学の理論でも実用場面での選択如何は実践目標次第です。建築構造計算ではニュートン力学が選ばれます。
性愛での通常の嫉妬と、 無意識の超自我的嫉妬
──フロイトの枠組について「実践の有効性」という言葉が出て来ました。とりわけ性愛について、どんな「実践の有効性」が考えられますか?
宮台 まず復習。「社会の代理人」として機能する家族関係・を通じて形成された、「社会の名において△△せよ」と指令機能を果たす自我のサブ装置が、超自我。家族が周囲にいなくても、社会の代理人として指令する超自我の機能が実装されれば「躾の成功」。ただし超自我は、規範の指令装置であると同時に、抑圧されたエネルギーの溜め込み装置でもあります。
「言葉で語られた法に損得で従う」定住に不可欠の法生活に、例外なく祝祭があった理由は、人類学と精神分析学を踏まえれば明らかです。法生活に従うよう自我を動機付ける超自我が不可避に蓄積する「逆転図式」の内圧(磁場)を、祝祭が程よくガス抜きして「規範図式」の力を回復し、集合的な法生活の持続可能性を強化する機能があったからです。
祝祭が集合的営みなのが重要です。言外・法外・損得外の祝祭時空は、ただの渾沌ではなく、法の時空に対する掟の時空だということです。掟は、祝祭時空の共同身体性や共通感情についての参照先です。平時の営みが所属集団の空気に従う法生活なのに対し、祝祭時の営みは、誰もが参照すると予期できる準拠集団(=想像的な所属集団)・の空気に従う掟生活です。
共同体の空洞化で、誰もが持つと予期できる準拠集団(想像的な所属集団)が消えると、掟の時空の消滅で、祝祭が不可能になり、「程よくガス抜き」できなくなります。すると必然的に、「規範図式」への過剰適応(=ガス抜きの不可能)よる「逆転図式」の過剰抑圧で、攻撃的暴発の危険が高まり、攻撃的暴発は「規範図式」に即した噴き上がりの形をとります。
それが先に話した、フーコーが集合的な反動形成として記述したビクトリア朝の「欲望禁圧の狂熱」のメカニズムです。同じメカニズムが、界隈が小さいとはいえクソフェミらの「欲望禁圧の狂熱」として再現されているというのが、僕の見立て。共通して言葉のラベルにステレオタイプを結合する「言葉の自動機械」による差別行為として具体化しています。
AV嬢は性被害者。風俗嬢は性被害者。売春は性被害(買春は性加害)。非当事者の物言いは非真実。男には「性愛が苦手な女の子のために」語る資格がない。拡げれば、非沖縄人に沖縄問題は語れない。非在日に在日問題は語れない。非弱者に弱者は語れない…云々。共通して、文脈への配視を欠くがゆえの、境界が曖昧な主語へのへばり付きが見られます。
フーコーは、欲望を禁圧しろ(「欲望=不快/禁欲=快」)という禁欲言説の狂熱に、欲望への狂熱(「欲望=快/禁欲=不快」)を見出します。先述の通り、フロイトの言説以前にイエスの言説(「姦淫を非難するお前達は目で姦淫している」)を反復しています。そしてイエスの言説は、ヨハネ福音書に従えば人々が「思い出す=思い当たる」ように語られます。
つまり、フロイトの反動形成は、理論以前に誰もが「思い当たる」ものです。だからゼミで「思い当たらないか」と訊くと、誰もが「思い当たる」と言います。その際ほぼ必ず出るのが「それは嫉妬みたいなものか」という質問です。素敵な直観です。ある意味そうです。ただし、通常語られる性愛的な嫉妬とは、似ていながら違う点もあるので、深めます。
性愛的な嫉妬には、男性的な嫉妬と女性的な嫉妬があります。「的な」とは社会的性別と必ずしも重ならないとの意味ですが、表現を圧縮して「男の」「女の」とします。男の嫉妬は「裏切りやがって」と女に矛先が向かう。女の嫉妬も「私の男に手出ししやがって」と女に矛先が向かう。そこから「男も女も<女>を参照する」というラカンの命題が出て来ます。
<女>とは想像的な「あるべき女」です。そこからのズレが男と女の憤激をもたらすのが、通常語られる性愛的な嫉妬です。反動形成に関わる超自我的な嫉妬も、ズレによる憤激です。でも何と何のズレかが違います。「凄くやりたいのにやれない自分」と「それを平気でやれている他者」とのズレです。要は「自分ができないことをやりやがって、チキショー!」です。
親や教員など「社会の代理人」から「先生の言うことを聞け」と言われれば「先生の言うことは聞きたくない」という欲望がインストールされた上で、抑圧されます。でも僕はADHDなので言うことを聞けません。するとクラスは「自分もそう思ってた」と賞賛する子と「ふざけるな、罰しろ」と憤激する子に二分されます。後者が超自我的な嫉妬です。
これが「勉強田吾作」問題に直結します。僕がいた中高進学校には「遊びも勉強もできる人>遊びだけできる人>勉強だけできる人>両方できない人」のスクールカーストがありました。この中で恨みベースになるのは「勉強だけできる人」。「どうせオイラは」的な自己像を抱えて代替的地位獲得競争に乗り出します。それがオタク的な営みの出発点でした。
それだけじゃ終らない。キャリア官僚にレクチャーしてきた経験から言うと、この界隈には「勉強だけできる人」が「遊びも勉強もできる人」を引きずり下ろす「勉強田吾作」の営みがあり、それゆえ「遊びも勉強もできる人」は早々にスピンアウトします。ちなみに「勉強田吾作」という言葉は、そうした観察の営みから高校時代に思い付いたものです。
こうした「勉強田吾作」に見られる超自我的な嫉妬が、今日のインセル(非自発的禁欲者)ないし斎藤環が言う「自傷的自己愛者」に一部重なるのは見易い。でも、気付きにくいのは、完全に同型の超自我的な嫉妬を自称フェミニストの一部に見出せることです。公共性を装うこの者たちの動機が、自分御大切のエゴイズムなので、「クソフェミ」と呼ぶのです。
エゴイズムだと言うのは、「どうせ自分にはできない」という「自己像の悪さ」による不安を反動形成で埋め合せる、臨床で強迫神経症(強迫性障害)に分類される営みだからです。クソフェミ言説に不安を煽られて、自己正当化的に「性愛に乗り出せない女の子」に留まり続ける人に、こうした分析の提示が極めて有効に機能してきた、という僕の経験があります。
と言うと、「どうせ自分は」という韜晦(=自傷的自己愛)に淫する「否定的自己像」を抱えた人が絶望しがちです。でもハードルは低い。だから第一部で「社会の時空から性愛の時空に入るとは、大人から子供に戻ること。そのためには…」という話をしました。子供でい続けられるか? 子供でい続けようとする相手を守れるか? それがあなたの最終目標です。
──第一部の映画の話題から、「子供であること」が言われていましたね。それはかつて子供であった私たち全員が理解できることですし、改めて気付かされました。今回は第一部、第二部に渡ってお話しくださり、ありがとうございました。次回は雑誌掲載もされますので、よろしくお願いします。



 Share
Share Tweet
Tweet Line
Line